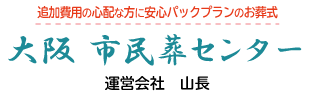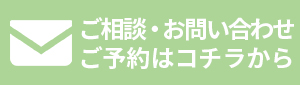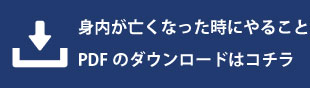親族や近い関係の人が亡くなったことで、学校や会社を休む場合は葬儀証明書が必要です。急なタイミングで必要となることが多いため、実際にどのようなタイミングでどこからもらうのか分からない方も多くいます。
今回の記事では、葬儀証明書や執行証明書のとり方を解説しています。また、発行の際の注意点もまとめているため、忌引きの手続きをスムーズに進めるためにも参考にしてみてください。
葬儀証明書とは
葬儀証明書は、葬儀社によっては「葬儀施行証明書」とも呼ばれ、忌引きの際の証明や弔慰金の申請時に使用します。
葬儀証明書の概要として、次の内容を解説します。
- 葬儀が執り行われたことを証明する書類
- 忌引きで休む時に必要となる
- 葬儀証明書の記載内容
それぞれの内容を詳しくみていきましょう。
葬儀が執り行われたことを証明する書類
お亡くなりになった方をお見送りする際、葬儀社から発行される葬儀証明書は、葬儀が行われたことを示す大切な書類です。書類名は葬儀社ごとに「葬儀証明書」「葬儀執行証明書」など若干の違いはありますが、基本的には、故人の名前や葬儀の日付、場所などが記されています。
葬儀証明書は、病院で医師が作成する死亡診断書とは異なる性質のものです。死亡診断書は医学的な死亡の証明である一方で、葬儀証明書は故人とのお別れの儀式が正式に執り行われたことを証明します。
そのため、葬儀証明書には法的な効力が一切ないことに注意しなければなりません。
忌引きで休む時に必要となる
自分と関係する人がお亡くなりになり葬式に参列する場合、職場や学校では忌引きとして休暇を取得できます。忌引きは、一般的な欠勤や欠席とは異なる特別な休暇扱いです。
忌引きの申請には、実際に葬式が執り行われたことを示す証明が必要となります。その際に重要な役割を果たすのが葬儀証明書です。葬儀証明書があることで、遺族や親族の方が、周囲の理解を得て安心して故人との大切なお別れの時間を過ごせます。
葬儀社が発行する葬儀証明書は、大切な儀式に参列するための公的な証明として広く活用されています。
葬儀証明書の記載内容
葬儀証明書には、お見送りをした方の名前をはじめ、しめやかに執り行われた葬儀の詳しい内容が記されます。
主な記載事項は次の通りです。
- 故人の名前
- 喪主様の名前
- 葬式が行われた日時や会場名
- 葬儀を執り行った葬儀社の名称
葬儀証明書は各葬儀社が独自に作成するものであり、統一された様式はありません。そのため、葬儀社によって記載される内容や書式が異なることがあるため注意が必要です。
もし忌引きの申請などで必要な情報が証明書に十分に記載されていない場合は、葬儀社に個別に相談することで、必要な追加情報を記載した証明書を発行してもらえるでしょう。最後の別れの証しとなる重要な書類のため、葬儀社は丁寧に対応してくれます。
葬儀証明書や執行証明書のとり方
葬儀証明書や執行証明書は急遽必要となるケースが多くあります。事前にとり方を確認しておくことでスムーズに手続きを進められるでしょう。
葬儀証明書や執行証明書のとり方として次の内容を解説します。
- 葬儀会社からもらう
- 葬儀で会葬礼状をもらう
- 死亡診断書や火葬(埋葬)許可証のコピーをとる
- 家族葬でも会葬礼状を発行してもらえる
それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。
葬儀会社からもらう
葬儀証明書は、一般的に葬儀を執り行った葬儀会社に申し出ることでスムーズに発行してもらえます。各葬儀会社では独自の証明書の様式を持っており、それぞれのフォーマットに合わせた形式で、故人の葬儀がいつ、どこで執り行われたのかを丁寧に証明してくれるでしょう。
葬儀証明書は公的な様式が定められているわけではないため、職場や学校から要望された記載事項がある場合、葬儀会社に相談すれば、可能な範囲で必要な情報を追加してもらえます。
ただし、葬儀会社の業務状況によっては、証明書の発行に時間を要するため、急ぎの場合は早めに依頼することをおすすめします。
葬儀で会葬礼状をもらう
葬式で参列者に渡される会葬礼状は、以前から忌引きの証明書類として広く使われてきました。会葬礼状がある場合は、改めて葬儀証明書を発行する必要はありません。
しかし、近年では家族葬をはじめとしたコンパクトなお葬式が増えていることによる葬儀の簡素化や形式の変化に伴い、会葬礼状が渡される機会が少なくなってきています。そのため、会葬礼状の提出を求められても、そもそも受け取っていない状況が増えているのが現状です。
このような背景から、葬儀社への証明書発行の依頼も増加しています。時代の変化とともに、証明する方法も変わってきているといえるでしょう。
死亡診断書や火葬(埋葬)許可証のコピーは適切ではない
亡くなった方の死亡診断書には、医師により詳しい経緯や病状、お亡くなりになった日時などが細かく記されています。どのような症状があり、どのように進行したのかなど、故人のデリケートな情報が含まれているため、忌引きの証明としてはふさわしくありません。
また、火葬(埋葬)許可証には、故人様の本籍地やご住所、生年月日など、多くの個人情報が記載されています。死亡診断書や火葬許可証は本来、別の目的で作成される大切な書類です。
一方、葬儀証明書は葬儀がいつどこで執り行われたか、忌引きに必要な情報だけを適切に記載しており、故人様やご遺族のプライバシーにも配慮されています。そのため、職場や学校への提出書類としては、葬儀証明書が最もふさわしい書類です。
家族葬でも会葬礼状を発行してもらえる
最近増えている家族葬でも、遺族以外の方が参列する場合には、会葬礼状を用意することがマナーです。
一方で、家族葬は主に遺族や親族を中心とした小規模なお葬式であり、一般の参列者の方は多くないのが特徴です。家族葬で、香典を辞退する場合には、会葬礼状の形式を採用しないパターンもあります。
会葬礼状が渡されない場合は、学校や会社を休むための証明として葬儀証明書が利用可能です。
葬儀証明書を発行する際の注意点
葬儀証明書を発行する際の注意点として次の内容が挙げられます。
- 法的な効力はない
- 葬儀後でも発行してもらえる
- 保険金を請求するための書類としては使用できない
注意点をあらかじめ理解した上で、葬儀証明書を発行してもらうとスムーズに手続きを進められます。
法的な効力はない
葬儀証明書は、葬儀社が独自に作成する証明書であり、行政機関などが発行する公的な書類とは異なります。葬式が執り行われたことを示す大切な書類ではありますが、法的な効力はありません。
戸籍の届出や各種手続きなど、公的機関への提出が必要な場合には、葬儀証明書ではなく死亡診断書や火葬許可証など、正式な書類が必要です。葬儀証明書は主に、職場や学校での忌引き申請など、葬式への参列を証明する用途として利用できます。
葬儀後でも発行してもらえる
葬式の最中だけでなく、葬儀が終わってから数日経過した後でも、葬儀証明書は葬儀社で発行できます。急に職場や学校から証明書の提出を求められた場合なども、葬儀を執り行った葬儀社に相談してみてください。
ただし、葬儀社の業務状況によっては、証明書の発行に時間を要することもあります。その場合は、職場や学校に対して、証明書の発行依頼は済んでいるものの、発行まで少し時間がかかる旨を伝えておくとよいでしょう。多くの場合、事情を説明すれば理解してもらえます。
保険金を請求するための書類としては使用できない
生命保険金の請求をする場合、葬儀証明書は保険金請求の正式な手続きでは利用できないことが一般的です。
多くの生命保険会社では、死亡の事実を証明する書類として、医師が作成した死亡診断書のコピーを提出することを求めます。ただし、保険会社によって必要となる書類は異なるため、具体的にどのような書類が必要かは、加入されている保険会社に問い合わせが必要です。
保険金の請求は大切な手続きですので、必要書類をしっかりと確認することをおすすめします。
まとめ
今回の記事では、葬儀証明書や執行証明書のとり方を解説しました。葬儀証明書は、葬儀社によっては「葬儀施行証明書」とも呼ばれ、忌引きの際の証明や弔慰金の申請時に使用します。
葬儀証明書は、病院で医師が作成する死亡診断書とは異なる性質のもので、葬儀証明書には法的な効力が一切ないことに注意しなければなりません。
葬儀証明書や執行証明書のとり方や、発行の際の注意点も紹介しているため、急に必要となった際に困らないためにも、参考にしてみてください。