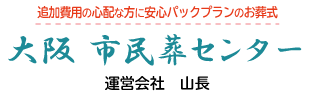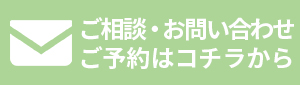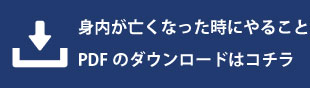葬儀で使用される六文銭が、どのようなものか気になっている方は多いのではないでしょうか。
大河ドラマでも取り上げられた真田家の家紋としても六文銭は知られています。
今回の記事では、六文銭の意味や由来、なぜ使用されているのかを解説します。
また、六文銭を実際に使用する場合の注意点や使用する手順も紹介しているため、葬儀を執り行う際の参考にしてみてください。
葬儀での六文銭とは
六文銭は、古くから葬儀で使われてきた副葬品の1つです。
亡くなった方のために用意される頭陀袋という小さな袋に入れられ、最期の旅立ちの際の持ち物として棺に納められます。
かつては本物のお金が使われていた時代もあったとされていますが、現代では火葬後の処理のことを考えて、特別に作られた模造品を使うのが一般的です。
実際の硬貨が火葬後に残ってしまうことや、もはや流通していない貨幣であることなどが、模造品を使う理由にあります。
大切な方を見送りする際の伝統として、六文銭は日本の葬送文化の中で受け継がれてきました。
形を変えながらも、故人の冥福を祈る想いとともに、現代に息づいている習わしです。
六文銭の由来
六文銭には、亡くなった方が三途の川を渡る際の渡し賃という由来があります。
いわば、最後の旅路に必要な交通費とも言えるものでした。
三途の川には、奪衣婆と懸衣翁と呼ばれる夫婦の番人がいると伝えられており、六文銭の渡し賃を持っていない方の衣服をはぎ取ってしまうと考えられていました。
そのため、人々はあの世への旅立ちの時のために、六文銭を用意していたのです。
六文銭の習慣は実際の生活にも影響を与えていました。
交通手段が今ほど発達していなかった時代、多くの旅人たちは、もしものときのことを考えて衣服に六文銭を縫い付けていたのです。
万が一道中で命を落とすことになっても、安らかな旅立ちができるよう、心遣いがされていました。
六文銭はなぜ使用されるのか
六文銭には、仏教の教えに基づいた深い意味が込められています。
六文銭の起源は「六道銭(ろくどうせん)」と呼ばれるもので、六つの異なる世界での生まれ変わりを表現していることが特徴です。
六つの世界とは、次の世界を示します。
- 地獄道
- 餓鬼道
- 畜生道
- 修羅道
- 人間道
- 天道
六文銭は、それぞれの世界で使われる銭として考えられていました。
このような世界観は、生まれ変わりの輪廻という仏教の教えと深く結びついています。
人々は、亡くなった方がどの世界に生まれ変わることになっても、必ず救いの手が差し伸べられますようにとの願いを込めて、三途の川の渡し賃として六文銭を用意するようになりました。
六文銭には亡き人の救済を願う、深い思いやりの心が込められています。
六文銭の江戸時代と今の価値
六文銭の「文」という単位は、今でいう円のような役割を果たしていました。
江戸時代は約300年と長い期間が続いた時代です。
その間、物の値段は大きく変動し、食事や住まい、給料など生活に関わるお金の使われ方も、現代とはかなり異なっていたとされています。
一般的に、当時の1文は今の30円から50円くらいの価値があったと考えられています。
そのため、六文銭の価値を今のお金に換算すると、およそ180円から300円ほどになるでしょう。
一見すると少額に思えるかもしれませんが、最後の旅路に必要な交通費とされていたことを考えると、大切な意味を持つ金額だったのではないでしょうか。
時代は違えど、お金に込められた想いは今も昔も変わりません。
六文銭は真田家の家紋
六文銭は、戦国時代を生きた真田家の象徴として、多くの人々に知られています。
六文銭の家紋は、真田幸隆によって採用されました。
真田幸隆は、死後の世界で使うとされる六文銭をあえて家紋に選ぶことで、「いつ戦場で命を落としても構わない」という武将としての覚悟を表現したと言われています。
真田家の印象的な家紋は、後に真田幸村へと受け継がれ、幸村もまた受け継いだ六文銭の家紋を背負って、数々の戦いに臨みました。
真田幸村の活躍は大河ドラマでも取り上げられ、多くの人々の心に深く刻まれています。
大河ドラマの影響もあり、今では「六文銭といえば真田家の家紋」のイメージが広く定着し、戦国時代を象徴する家紋の1つとして、現代にも鮮やかに残っていることが特徴です。
葬儀で六文銭を使用する際に注意するポイント
葬儀で六文銭を使用する際に注意するポイントとして次の内容が挙げられます。
- 本物の貨幣は使用しない
- 木製または紙製でもよい
- 仏教以外では使用しない
それぞれのポイントに気をつけて葬儀に臨む必要があるでしょう。
本物の貨幣は使用しない
六文銭を葬儀で使用する際の注意点として、本物の貨幣は使用しないことが挙げられます。
本物のお金を変形したり傷つけたりすることは法律で禁止されているため、実際の紙幣や硬貨を棺に入れられません。
代わりに、おもちゃのお札を使うなど、さまざまな方法で代用できます。
大切なのは形ではなく、故人への想いを込めることだと言えるでしょう。
また、多くの葬儀社では、六文銭の文化を取り入れられるように、六文銭の代わりとなる副葬品を準備しています。
伝統的な慣習を大切にしながらも、現代の法律に沿った形で、故人を見送りする儀式が執り行われています。
木製または紙製でもよい
葬儀で六文銭を準備する際、本物の貨幣が使えない代わりに、木製や紙製の代用品を使う方法があります。
木製や紙製の素材は火葬の際も安心して使えるため、副葬品としてとても適していることが特徴です。
今では、葬儀社の多くが、遺族の気持ちに配慮して、六文銭の代用品をサービスの1つとして取り揃えています。
また、お好みの品を選びたい方のために、オンラインショップでも購入できるようになり、より自由に選択可能です。
このように、現代に合わせた形で受け継がれている六文銭の習わしは、大切な方への最後の別れの気持ちを表現する手段として、残っています。
素材は違えど、そこには変わらぬ想いが込められているでしょう。
仏教以外では使用しない
六文銭を含めて、副葬品を葬儀で使用する際は、宗教による違いを知っておかなければなりません。
六文銭は仏教の教えに基づいた副葬品として親しまれてきたもので、葬式の形式によって使い方が異なります。
それぞれの宗教には、独自の死生観や死後の世界に対する考え方があります。
そのため、神道やキリスト教、イスラム教など、仏教以外の宗教では、六文銭を棺に納める習慣は一般的ではありません。
大切な方との最後の別れの時には、故人の信仰に寄り添った形で送り出すことが何より大切です。
仏教以外の葬儀では、それぞれの宗教で大切にされている方法で、心を込めてお見送りすることをおすすめします。
葬儀で六文銭を使用する方法
葬式で六文銭を使用する際の手順は次の通りです。
- 頭陀袋に、プリントされた紙など六文銭を模したものを入れる
- 六文銭を入れた頭陀袋を首から下げる
まずは、お金の絵が印刷された紙や、木製のもの、あるいはおもちゃのお金など、六文銭の代用品を準備します。
形に決まりはなく、大切な想いを込める副葬品として使われるものであれば問題はありません。
頭陀袋と呼ばれる葬式で使われる特別な袋があり、儀式が行われた後に、六文銭をその中に入れます。
そして、亡くなった方の首にかけ、胸元に優しく添えられるように置きます。
頭陀袋を首からかける理由は、あの世への旅路で必要なものをいつも傍らに置いていただきたいという、深い願いが込められているためです。
胸元に添えられた六文銭には、亡くなった方が安らかに旅立たれますようにという、心からの祈りが込められています。
まとめ
今回の記事では、葬儀で使用される六文銭を解説しました。
六文銭は、古くから葬儀で使われてきた副葬品の1つです。
亡くなった方のために用意される頭陀袋という小さな袋に入れられ、最期の旅立ちの際の持ち物として棺に納められます。
六文銭には、亡くなった方が三途の川を渡る際の渡し賃という由来があり、最後の旅路に必要な交通費とも言えるものです。
六文銭を葬儀で使用する際の注意点として、本物の貨幣は使用しないことが挙げられます。
本物のお金を変形したり傷つけたりすることは法律で禁止されているため、実際の紙幣や硬貨を棺に入れられません。
葬儀社がオプションとして用意する場合や、オンラインショップで購入できる場合などもあるため、事前にどのような形で用意するか検討しておくとよいでしょう。
六文銭を使用する際の注意点や手順も解説しているため、葬儀で副葬品として使用する場合は参考にしてみてください。