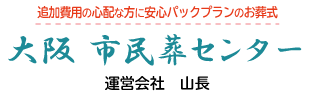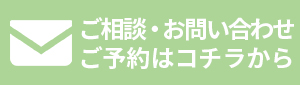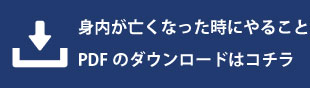創価学会で執り行われる葬儀として友人葬があります。友人葬には参列するにあたっていくつかの注意点があるため、事前にある程度把握した上で参列することが望ましいでしょう。
今回の記事では、友人葬の特徴を解説しています。また、式の流れや香典の扱いも紹介しているため、これから友人葬に参列する方は参考にしてみてください。
友人葬の特徴

友人葬は創価学会の特徴的な葬儀形式として知られています。創価学会は、故人の成仏は生前の信仰に基づくものであるとする考え方から、僧侶を招かない葬儀形式を採用していることが特徴です。
僧侶を呼ばないこと、戒名をつけないこと、しきみが中心のことなど特徴を詳しく解説します。
僧侶は呼ばない
友人葬の特徴として、僧侶を招かない点が一般的な仏式葬儀との顕著な違いとして挙げられます。友人葬は、儀式の進行役は僧侶ではなく、儀式に精通した幹部が導師を務めることが多い傾向です。
導師は本質的に友人代表の位置づけのため、一般的な仏式葬儀で行われるようなお布施の授受は行われません。僧侶を招かない形式は創価学会の教義に基づいており、故人の成仏と葬儀形式との間に関連性がない考え方を反映しています。
故人に戒名をつけない
友人葬の特徴として、故人に戒名をつけないことが挙げられます。戒名は日本の仏教における伝統的な儀式の一部であり、亡くなった人に対して新たな名前を授けるものですが、創価学会では独自の信仰体系を持つため、戒名の慣習を採用していません。
友人葬は、故人が生前使用していた名前のままで弔われます。そのため、位牌に記載されるのも戒名ではなく、故人が生前使っていた名前です。また、戒名の授与がないため、仏式葬儀で一般的に発生する戒名料も必要ありません。
祭壇はしきみが中心
友人葬の特徴の1つが、祭壇の装飾にしきみが使用される点です。しきみは黄色い花を咲かせる常緑樹で、花から葉、茎、根に至るまでの全体に猛毒を持つ植物です。しきみは土葬が一般的だった時代に、毒性によって野犬などの野生動物が墓を荒らすことを防ぐ実用的な目的から、供花として使われてきました。
一般的な仏式葬儀の祭壇では、菊の花を中心として、故人が生前好んでいた花や季節の花々が色とりどりに飾られることが多いのに対し、友人葬は、しきみを主要な素材として使用し、白い花のアレンジメントを加えながら装飾するのが一般的なスタイルです。
しきみを中心とした装飾は、簡素でありながらも厳粛さを保ち、伝統的な仏式葬儀とは一線を画す雰囲気を創出しています。
友人葬の流れ

友人葬は次の流れで執り行われます。
- 開式の辞
- 読経・唱題
- 焼香
- 御祈念文・題目三唱
- 弔慰文・弔電の紹介
- 導師の挨拶
- 謝辞
- 題目三唱
- 閉式の辞
- 出棺
それぞれの流れの詳細を解説します。
開式の辞
開式の辞は葬儀の始まりを告げる重要な役割を担っています。開式の辞には、これから行われる式の進行についての説明や、多忙な中で参列してくださった方々への感謝の言葉も含まれます。また、故人がどのような人物であったか簡潔な紹介も行われることが一般的です。
開式の辞は、参列者全員が故人を偲ぶ場に心を集中させ、これから始まる葬送儀礼に向けて気持ちを整える時間です。
読経・唱題
友人葬は、導師を中心として参列者全員で読経と唱題が行われます。読経とは具体的に法華経の中から方便品と寿量品の自我偈を2回にわたって読誦することを指します。一方、唱題は「南無妙法蓮華経」と題目を声に出して唱えることです。
読経・唱題の儀式は、創価学会の信仰の核心部分を表現するものであり、故人の魂の安らぎと成仏を導師が中心となって願う重要な時間です。一般的な仏式葬儀の読経に相当するものですが、創価学会独自の友人葬としての独自性が表れています。
焼香
友人葬の焼香は通常、1回目の自我偈読誦が行われている間に執り行われることが一般的です。焼香の順番には決まりがあり、最初に導師と副導師が焼香を行い、次に故人の親族、そして最後に一般の参列者の順序で進められます。
友人葬でも、焼香の儀式は故人を偲び、別れを告げる重要な時間として位置づけられており、参列者一人ひとりが故人との思い出や感謝の気持ちを込めて焼香を行います。
御祈念文・題目三唱
友人葬の流れで、御祈念文・題目三唱は儀式の締めくくりとなる重要な要素です。全参列者による焼香が終了し、導師が鈴を鳴らした後、追善供養の祈念が行われます。追善供養とは、生きている者が故人の冥福を祈り、供養を捧げる行為です。
祈念が終了すると、参列者全員で題目を三回唱和します。御祈念文・題目三唱の儀式によって、参列者は心を1つにして故人の旅立ちを見送り、同時に残された者たちの結束を確認する時間となるでしょう。
弔慰文・弔電の紹介
御祈念文と題目三唱の儀式が終了した後、次の段階として弔慰文や弔電の紹介が行われます。弔慰文とは手紙形式で書かれた哀悼の意を表す文章であり、故人との思い出や感謝の気持ちが綴られていることが一般的です。
一方、弔電は電報形式で送られてくる短いメッセージですが、同じく故人への哀悼の意が込められています。弔慰文や弔電は、直接参列できなかった方々からの最後のメッセージとして、故人や遺族への敬意と思いやりを示すものです。
導師の挨拶
友人葬の導師の挨拶は、創価学会の教義や思想に基づいた内容が語られます。故人の生き方や信仰、生前の功績などが創価学会の価値観と関連づけて語られることが一般的です。
導師の挨拶にかける時間は、担当する導師によって異なります。短く簡潔に終える導師もいれば、故人との思い出や創価学会の教えを長く語る導師もいます。
謝辞
友人葬の謝辞は、喪主か親族の代表者によって述べられます。謝辞は参列者への感謝の言葉が述べられるとともに、故人の生前の思い出や家族との絆にも触れられることが一般的です。
謝辞を述べる時間は比較的短いものの、故人の最も身近な家族や親族の生の声として、参列者の心に深く響くものとなるでしょう。さまざまな儀式や形式的な進行が続いた後だからこそ、素直な感謝の言葉は特別な意味を持ちます。
題目三唱
題目三唱は、儀式の締めくくりとして、導師が鈴を鳴らして合図を出し、合図に合わせて参列者全員で題目を3回唱和します。参列者全員の心を1つにし、故人の冥福を祈るとともに、残された人々の絆を確認する意味合いを持っています。
閉式の辞
閉式の辞は主に葬儀社の司会者や導師が担当し、式の終了を正式に告げることが役割です。感謝の言葉とともに、告別式後の流れや火葬場への移動方法、精進落としの会場案内など、今後の段取りに関する実務的な連絡事項も伝えられます。
出棺
告別式の儀式が終了すると、参列者が「南無妙法蓮華経」を唱える中、しきみなどの供花を棺に納めながら最後のお別れの儀式が行われます。この時間は、参列者一人ひとりが故人への最後の別れを告げる貴重な機会です。
その後、数名の男性近親者によって棺が霊柩車へと運ばれます。出棺の直前には喪主から挨拶があり、感謝の言葉とともに今後の流れの案内がなされることが一般的です。
友人葬の香典は不要?

原則として、友人葬では香典は不要とされてきました。これは創価学会の考え方に基づくもので、葬儀を故人と親しい人々が集まって送る場としての「友人葬」という名称の通り、形式よりも心の交流を重視する精神を反映しています。
一方で、香典を持参することを禁止する明確な規則はなく、また受け取りを拒否する決まりもありません。近年では、弔意の表現として自主的に香典を持参する参列者が増加傾向にあります。このような変化に伴い、香典返しも一般的な葬儀と同様のマナーで行われるようになってきているのが現状です。
まとめ
今回の記事では友人葬の解説をしました。友人葬は創価学会の特徴的な葬儀形式として知られています。創価学会は、故人の成仏は生前の信仰に基づくものであるとする考え方から、僧侶を招かない葬儀形式を採用していることが特徴です。
祭壇の装飾にしきみが使用される点も特徴の1つで、一般的な仏式葬儀の祭壇では、菊の花を中心として、故人が生前好んでいた花や季節の花々が色とりどりに飾られることが多いのに対し、友人葬は、しきみを主要な素材として使用します。
友人葬の一通りの流れの紹介や、香典に対する扱いも解説しているため、これから友人葬に参列する方は参考にしてみてください。