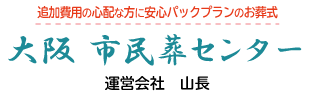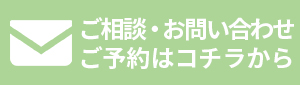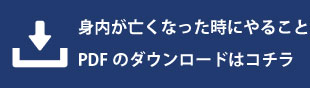大阪市で経営者の社葬・お葬式をお考えの方へ
経営者には経営者に
相応しいお別れを
社員や家族のために尽くし、数々の決断を重ねながら、会社をここまで導いてきた——
その歩みは、簡単な言葉で語れるものではありません。
経営者という立場は、喜びも重圧も大きく、孤独な決断の連続だったことでしょう。
だからこそ、最期のお別れには、その人生を深く讃え、関わってきた人々が感謝と敬意を込めて見送る「かたち」が必要です。
私たちは、経営者としての功績だけでなく、一人の人としての想いや背景にも寄り添いながら、心に残るお葬式をご提案いたします。

こんなお悩みありませんか?
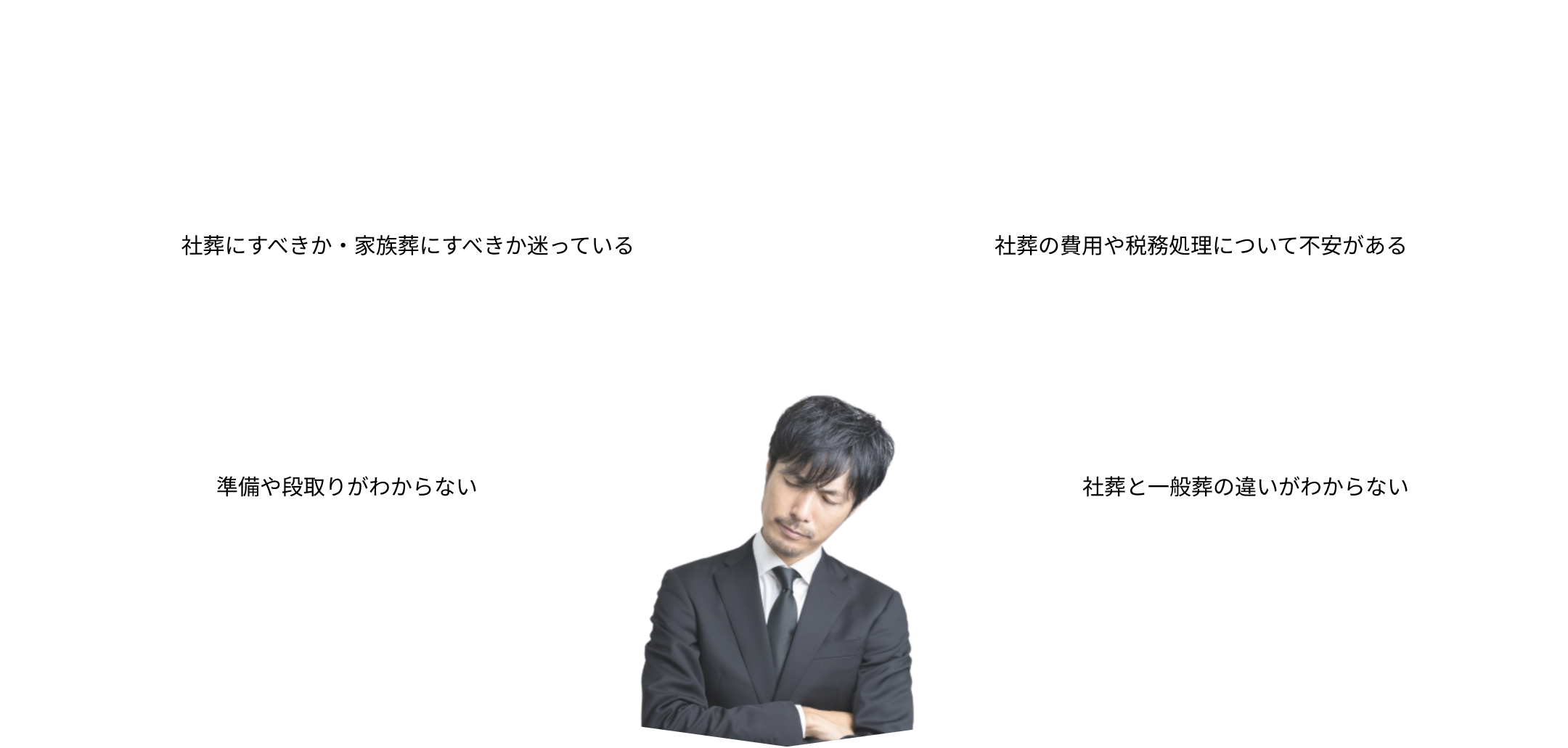
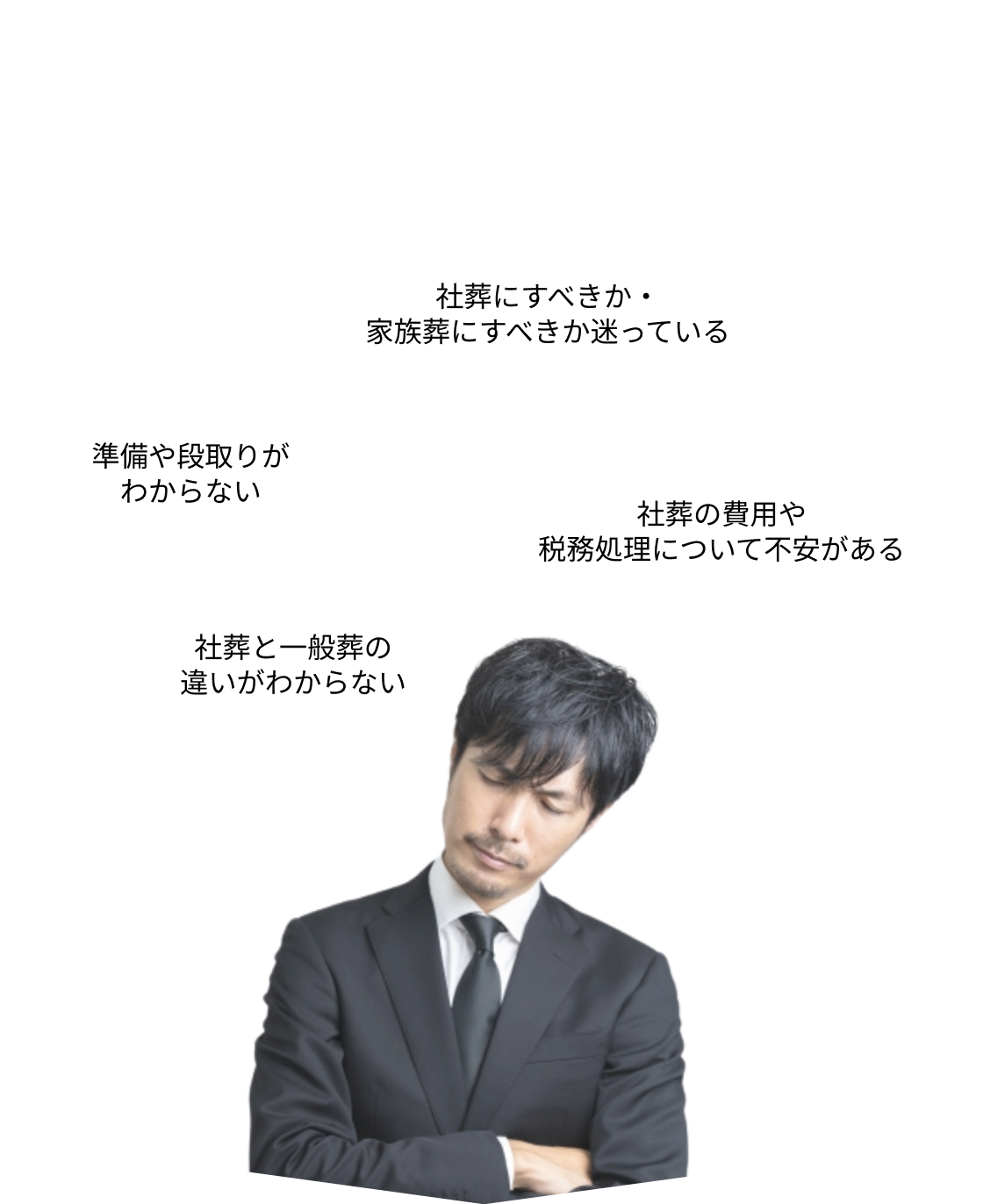
大切な経営者様を送り出す社葬には、故人への敬意と会社としての誠意が求められます。
ご遺族の想いも、企業の立場も、私たちが丁寧に橋渡しします。
経営者のお葬式のご依頼・ご相談はこちらから
大阪市で経営者のお葬式・
社葬を行える会場のご案内
大阪市立やすらぎ天空館

-
大阪市立やすらぎ天空館は、大阪市阿倍野区にある公営の斎場です。近代的な建物は、一見するとホテルのような感じです。ご近所の方には「阿倍野斎場」と呼ばれており、大阪市内では広く知られている斎場です。やすらぎ天空館の式場は中型の式場が2つあり、座席数は200席あります。社葬など大きなお葬式を執り行う際には、2つの中式場をつなげて大式場として利用することもできます。大式場で利用する場合は座席数が400席となり、最大1,000人まで収容が可能です。
やすらぎ天空館は、大阪市内の中心部にあり、最寄駅から徒歩3分とアクセスもしやすく、弔問や会葬でも行きやすい立地にあります。駅周辺には大型の商業施設があり、とても便利です。大阪府大阪市内での社葬や経営者のお葬式をお考えの企業様にとって、アクセス面・収容人数ともに良い式場です。。
- 住 所
- 大阪市阿倍野区阿倍野筋4−19−115
- アクセス
- OsakaMetro谷町線、阪堺電軌上町線「阿倍野駅」より徒歩3分
大阪シティバス「あべの筋四丁目」バス停下車、徒歩すぐ
経営者のお葬式・社葬プラン一覧
大阪市で経営者のお葬式や社葬をお考えの企業様向けに、規模やご予算に応じた市民葬プランをご用意しています。
社葬と一般葬の違い
| 社葬 | 一般葬 | |
|---|---|---|
| 主催者 | 会社(葬儀委員長を設ける) | 遺族(喪主も兼ねる) |
| 喪主 | 遺族(ただし葬儀の責任者は葬儀委員長) | 遺族(通常は配偶者や⼦) |
| 費用負担 | 会社が全額または一部負担 | 遺族が全額負担 |
| 参列者の範囲 | 社員、取引先、業界関係者など広範囲 | 親族、友⼈、知⼈など個⼈的な関係者 |
| 目的 | 故人の成功を称え、社内外に後継や事業継続を示す機会 | 故⼈との最後のお別れ |
| 規模 | 中規模〜大規模が一般的 | ⼩〜中規模が多い |
| 香典の扱い | 辞退するケースが多い(税務上の理由) | 遺族が受け取る |
| 社葬 | |
|---|---|
| 主催者 | 会社(葬儀委員長を設ける) |
| 喪主 | 遺族(ただし葬儀の責任者は葬儀委員長) |
| 費用負担 | 会社が全額または一部負担 |
| 参列者の範囲 | 社員、取引先、業界関係者など広範囲 |
| 目的 | 故人の成功を称え、社内外に後継や事業継続を示す機会 |
| 規模 | 中規模〜大規模が一般的 |
| 香典の扱い | 辞退するケースが多い(税務上の理由) |
| 一般葬 | |
|---|---|
| 主催者 | 遺族(喪主も兼ねる) |
| 喪主 | 遺族(通常は配偶者や⼦) |
| 費用負担 | 遺族が全額負担 |
| 参列者の範囲 | 親族、友⼈、知⼈など個⼈的な関係者社 |
| 目的 | 故⼈との最後のお別れ |
| 規模 | ⼩〜中規模が多い |
| 香典の扱い | 遺族が受け取る |
経営者のお葬式・社葬での
注意点
-
その1
遺族の意向を最優先に

社葬を検討する場合でも、まずは遺族の意向を尊重することが⼤切です。遺族の同意なく社葬を決定すると、トラブルの原因となります。
-
その2
⼗分な準備期間の確保

社葬は関係者への連絡や会場⼿配など、⼀般葬よりも準備に時間がかかります。急な訃報に備え、対応フローを整備しておきましょう。
-
その3
事前の社内規定整備
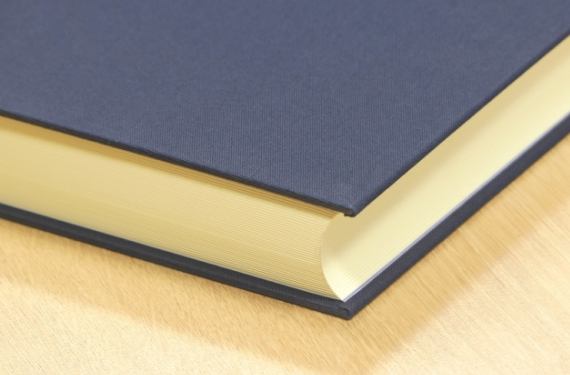
社葬の対象者や費⽤負担の範囲などを事前に社内規定として明⽂化しておくことで、混乱を防げます。
-
その4
税務上の取り扱い

社葬費⽤を経費として計上する場合、取締役会での決議と議事録の作成が必要です。また、すべての費⽤が損⾦算⼊できるわけではないことに注意が必要です。
経営者のお葬式のご依頼・ご相談はこちらから
経営者のお葬式・社葬の
代表的な方式
合同葬・お葬式
合同葬とは、遺族と会社が共同で喪主‧施主となって執り⾏う葬儀です。
⼀度の葬儀で社内外の関係者にお別れの機会を提供できるため、効率的な⽅法といえます。
-
合同葬のメリット
- 葬儀を⼀度で済ませられる(遺族の負担軽減)
- 費⽤を会社と遺族で分担できる
- 会社関係者と遺族の友⼈‧知⼈が⼀堂に会する
-
合同葬のデメリット
- 参列者が多くなるため、遺族が⼗分に悲しみに向き合えない
- 遺族と会社の意向が異なる場合、調整が難しい
- 規模が⼤きくなりがちで費⽤総額も増える
-
こんな方におすすめ
- 中⼩企業の経営者で、会社と家族の関係が近い場合
- 遺族が多くの関係者にお別れの機会を設けたい場合
- 葬儀を⼀度で済ませたい場合
密葬・お別れの会
密葬とは、ご家族やごく親しい方々のみで静かに執り行う葬儀のかたちです。通夜や告別式といった一般的な儀式は行わず、
後日「お別れの会」などの形式で改めて故人を偲ぶ機会を設けるケースが多くなっています。
故人の意志やご家族のご希望を大切にし、落ち着いた環境の中でゆっくりとお見送りができるスタイルとして選ばれています。
-
密葬・お別れの会のメリット
- 故人やご家族のプライバシーを守れる
- 日程や進行を柔軟に調整できる
- 参列者の負担を軽減できる
-
密葬・お別れの会のデメリット
- 参列を希望する方が参列できない可能性がある
- 社葬や公的な対応には向かない場合も
- 葬儀の進行に十分な時間を取りにくい場合がある
-
こんな方におすすめ
- 葬儀を落ち着いた雰囲気で執り行いたい方
- ご家族や近しい方だけで静かにお見送りしたい方
- 後日、改めてお別れの会を設けたいとお考えの方
- ご本人のご意向でシンプルな形の葬儀を希望された場合
家族葬
家族葬とは、ご家族やごく親しいご親族・友人のみで行う、小規模であたたかな葬儀のかたちです。
故人とのお別れの時間を静かに、心ゆくまで過ごしたいというご希望から、近年多くの方に選ばれるようになっています。
一般葬に比べて参列者が少ないため、準備や対応の負担が少なく、精神的にも落ち着いて故人を偲ぶことができます。
-
家族葬のメリット
- 気兼ねなくお見送りができる
- 費用を抑えやすい
- 参列者対応の負担が少ない
-
家族葬のデメリット
- 葬儀の案内を受けなかった方への配慮が必要
- 後日弔問や香典を受けることがある
-
こんな方におすすめ
- 故人と静かに、心からのお別れをしたい方
- 参列者対応や儀式の形式にとらわれたくない方
- 身内だけで温かい雰囲気の葬儀を行いたい方
- 葬儀の費用や規模をコンパクトに抑えたい方
一般葬(大型)
-
一般葬(大型)のメリット
- 故人との関係者が広く集まれる
- 故人の功績や人柄をしっかり伝えられる
- 社会的な礼節を重んじられる
-
一般葬(大型)のデメリット
- 準備や手配に時間と手間がかかる
- 費用が高くなりやすい
- プライベートな時間がとりにくい
-
こんな方におすすめ
- 社会的なつながりが多い方(会社経営者・地域活動に積極的だった方など)
- 故人の人生を多くの人に伝え、しっかりと送り出したいご遺族
- 一般的な形式で、礼節を重んじた葬儀を希望される方
大阪市で経営者のお葬式・
社葬にかかる費用
-
社葬(お別れの会)
会場費 30万円〜 祭壇・装飾費 60万円〜 案内状の印刷・発送費 20万円〜 受付・記録台設置費 10万円〜 返礼品費 40万円〜 司会者費用 10万円〜 接待費(飲食費) 40万円〜 その他(人件費、交通費等) 40万円〜 合計目安
250万円〜500万円
-
合同葬
基本葬儀費用(葬儀社への支払い) 130万円〜 寺院へのお布施 40万円〜 火葬場使用料 5万円〜 通夜・告別式会場費 40万円〜 飲食接待費 60万円〜 返礼品 40万円〜 その他(供花、弔電等) 35万円〜 合計目安
350万円〜600万円
社葬費用の考え方
●税務上、経費として認められる社葬費⽤の主な項⽬
訃報通知の新聞広告料、案内状の作成‧発送費⽤、祭壇料・葬儀場の使⽤料、宗教者へのお礼(お布施など)、参列者へのハイヤー代および送迎バス代、参列者への御礼(礼状および粗品)、社葬‧合同葬を⼿伝った社員に対する簡単な慰労会費⽤‧⾷事代、葬儀社警備などの⼈件費、写真‧ビデオ撮影料、など
●経費として認められない費⽤
戒名料、墓⽯の購⼊費⽤、仏壇‧位牌の購⼊費⽤、遺族の私的な接待費⽤
経営者のお葬式・社葬プランに
含まれるもの

生花祭壇

寝台車
(病院〜自宅)ご逝去の際に病院・施設・警察署から搬送するお車です 
寝台車
(自宅〜式場)安置場所から式場・式場から火葬場へ出棺するときのお車になります 
ドライアイス
故人様のお身体を保冷する物 
高級布張棺

仏布
ご納棺の際に故人様にお着せる白い着物です。(旅支度・死装束)とも言われます。 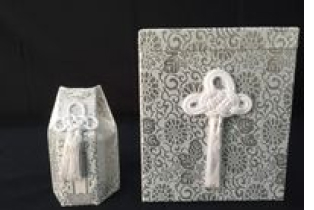
骨箱
本骨箱は故人様ののど仏を納め、本山(お寺)へ納められます。胴骨箱は本骨よりお骨を多く拾いお墓に収められる事が多いです。 
遺影写真
お葬式の際に祭壇に飾られる故人様のお写真になります。お写真により加工・着せ替えが出来ます。 
式場案内板
式場正面に故人様のお名前や通夜・お葬式のお時間が記載された物です。 
後飾りセット
仏式でのお葬式の場合に35日・49日まで故人様をお供養する仏具の台のセットです。 
故人様預かり霊安室
(付き添い不可)ご逝去の際に自宅安置が出来ない場合に故人様だけを預かる霊安室になります。(付添不可・面会可 要予約) 
出棺用花束
出棺の際に故人様と最後のお別れをする意味でお棺の上に手向ける花束のことです。 
役所/火葬 手続き代行
死亡診断書・死体検案書をお預かりして役所へ提出し火葬許可証に変えて斎場へ式場・火葬の申込みを代行させて頂いております。 
受付セット

焼香設備

セレモニースタッフ
宗教者様のお着換えや遺族・親族様・弔問・会葬者接待係、式場の清掃などを対応する係員です。 
司会
お通夜・お葬式を進行する係(弔電拝読・焼香順位・喪主様挨拶の代弁などする係員) 
運営スタッフ
経営者のお葬式のご依頼・ご相談はこちらから
経営者のお葬式・社葬の流れ
一般葬は、ご逝去後すぐにご遺族が葬儀を手配し、通夜・告別式を数日以内に行うのが一般的です。
一方で社葬は、まずご遺族による「密葬」を行った後、数週間〜1か月ほどかけて準備を進め、
企業が主催する「社葬本葬」を改めて執り行います。
社葬では、社葬委員会の設置や案内状の送付、式場・進行の手配など、社内外との調整を踏まえた計画的な流れが必要です。
準備期間と手順が異なる点が、一般葬との大きな違いです。


経営者のお葬式・社葬前に行うこと
| 社葬取扱規程の整備 | 社葬の対象者や費⽤負担範囲、実施⼿順などを予め社内規定として明⽂化しておくことで、緊急時の混乱を防ぎます。 |
|---|---|
| 緊急連絡網の整備 | 万が⼀の際の連絡体制を整備し、誰がどのような役割を担うか明確にしておきます。 |
| 葬儀社との関係構築 | 信頼できる葬儀社と事前に関係を築いておくことで、緊急時にスムーズな対応が可能になります。 |
| 基本的な葬儀プランの検討 | 社葬の規模や形式、予算の⽬安などを事前に検討しておきます。 |
| 弔事マニュアルの作成 | 社葬実施の⼿順や役割分担、チェックリストなどをまとめたマニュアルを作成しておくと安⼼です。 |
| 経営者本⼈の意向確認 | 可能であれば、経営者本⼈の葬儀に対する意向を事前に確認しておくことも重要です。 |
経営者のお葬式・社葬後に行うこと
| ️御礼の挨拶回り | 来賓や弔辞を頂いた⽅など重要な参列者へは、社葬終了後3⽇以内を⽬安に御礼の挨拶に伺います。 |
|---|---|
| 会葬御礼状の発送 | 参列者全員に御礼状を送付します。供花や弔電を頂いた⽅にも送付します。 |
| 新聞への会葬御礼広告掲載 | 社葬の規模が⼤きい場合は、新聞に会葬御礼の広告を掲載することもあります。 |
ご依頼から葬儀までの流れ
- 1
ご相談・お問合せ
お電話またはフォームにてご連絡ください。
「社葬は初めてで何から始めたらいいか分からない」という方もご安心ください。
ご希望の日時・場所・宗派やご要望を丁寧にヒアリングさせていただきます。 - 2
社内検討・方針決定
ご遺族や役員と相談のうえ、社葬として執り行うかを社内で協議。
必要に応じて社葬委員会を設置し、運営体制や費用負担のルールを明確にします。
※必要に応じて、当社スタッフが打合せに同席することも可能です。 - 3
プラン提案・御見積
ご希望の規模や式場、式の形式(宗教儀式の有無)に応じて最適なプランをご提案します。
お見積書も明確に提示し、ご納得いただけた段階で正式なご契約となります。 - 4
準備・ご案内の手配
・式場・僧侶・祭壇・供花の手配
・ご案内状(社内・社外)や新聞掲載の文案作成
・弔辞を依頼する関係者への調整
・受付・会計・案内係などの役割分担もご支援いたします
社葬に不慣れな企業様でも、当社が細部までサポートいたします。 - 5
通夜・葬儀当日
当日はスタッフが常駐し、司会進行・焼香案内・ご導線の誘導などもすべて対応。
社葬の品格を保ちつつ、故人への敬意を込めて式が円滑に進行するよう運営いたします。 - 6
アフターフォロー
・香典返し・会計処理・弔問客リストの整理
・挨拶状の発送
・初七日・四十九日など法要のご相談
・ご希望があれば社史や追悼ページの制作も可能です
※ご希望があれば、ご遺族側と企業側の調整役も弊社が担当いたします。※社葬だけでなく、合同葬・お別れの会形式にも対応可能です。
大阪府大阪市の企業様からの社葬・経営者のお葬式に関するご相談を多くいただいています。
「規模や費用の相場が知りたい」といったお声も少なくありません。
進行内容までトータルでご提案し、企画段階から当日の運営まで丁寧にサポートいたします。
よくあるご質問
- 社葬と⼀般葬のどちらを選ぶべきか迷っています
- 故⼈の⽣前の意向や遺族の希望を第⼀に考えるべきです。社葬は会社の規模や故⼈の功績、取引先との関係性なども考慮して決定します。特に会社への貢献度が⾼く、社内外に幅広い⼈脈がある場合は社葬が適している場合が多いです。まずは遺族と会社側で⼗分に話し合いましょう。
- 社葬にはどれくらいの準備期間が必要ですか?
-
2週間〜1か月程度の準備期間が必要です。
日程や会場の調整、案内状の作成、式次第の決定など多くの準備がありますが、内容によっては短期間での対応も可能です。
まずは早めにご相談いただくことをおすすめします。
- ⾹典は辞退すべきですか?
-
必ず辞退しなければならないという決まりはありません。
しかし最近では、香典や香典返しを辞退する企業も増えています。理由としては、参列者への負担軽減や、平等性の配慮が挙げられます。
会社の方針や関係者とのバランスを考慮して判断されるとよいでしょう。
- ⼩規模企業でも社葬は可能ですか?
-
はい、小規模な企業様でも社葬は可能です。
社葬の規模や形式は自由に調整できるため、ご予算や参列者数に合わせて無理なく実施できます。
「会社としてしっかりと送り出したい」という想いがあれば、企業規模に関わらず社葬を行うことができます。
- 社葬の費⽤はすべて会社の経費になりますか?
-
一部は経費として処理できますが、すべてが経費になるわけではありません。
会社が業務上必要と判断した費用(会場費や案内状印刷費など)は「福利厚生費」や「交際費」として経費計上が可能です。
ただし、香典返しや遺族への支出などは会社の経費と認められない場合があります。
詳細は、顧問税理士や会計士への確認をおすすめします。